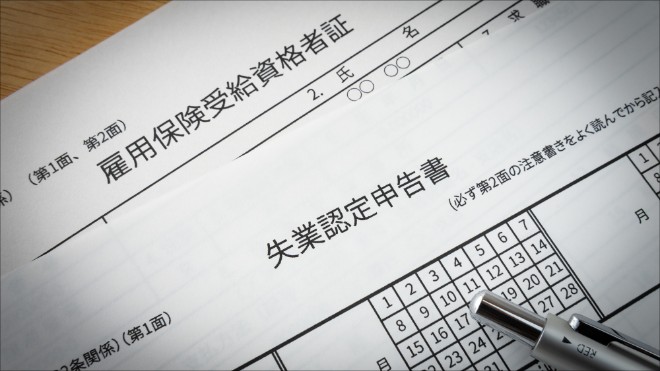定年後、一般的には収入がぐっと少なくなります。「果たして今と同じような暮らし向きを続けられるだろうか」と不安になっている人はいませんか。老後、いくら必要になるかは、収入や家族構成によって違ってきます。シミュレーションしようと思っても、何にいくらかかるのかがよくわからないという方のために、具体的にかかる費用について解説します。また、今のうちに準備しておくべきこともご案内します。
老後にかかる資金の必要額
老後、夫婦二人で亡くなるまで生活をしていくためには、いくら必要かご存知でしょうか。公的年金をもらうとしても、ほかに2,000万円から3,000万円の資金が必要といわれています。
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦世帯における月々の支出は、平均27万円程度となっています(総務省調査)。これに対して公的年金などの給付は、夫婦二人で平均して19万円です。つまり、シニアであっても働かず、個人年金もない場合は、月々8万円の赤字となります。
夫65歳、妻60歳の夫婦が90歳まで生きるとしましょう。すると、25年間も8万円の赤字が出続けることになります。
持ち出しの合計は、
8万円×12ヶ月×25年間 = 2,400万円
となります。
ただ生活するだけでは、潤いのある人生とはいえません。ときには旅行もありますし、冠婚葬祭といったつきあいも必要です。すると、やはり「老後に必要な資金は、2,000万円から3,000万円」ということになります。
老後資金2000万円問題とは?老後に必要な資金の内訳や今からできること
老後に得られる収入
老後に得られる収入には、どんなものがあるでしょうか。代表的なものを挙げますので、自分にどれが当てはまるか、考えてみましょう。
- 公的年金
65歳から公的年金を受け取ることができます。希望すれば60歳以降は繰り上げ受給も可能ですが、減額となります。 - 個人年金
個人年金保険をかけていた人は、契約時に設定した年齢から保険金を受け取ることができます。 - 企業年金
会社側が、社員の福利厚生の一環として給与天引きの形などでかけている年金です。公的年金を補う形で支払われたり、退職金として支給されたりします。年金の種類や金額は、会社によって違います。企業年金制度のない会社もあります。 - 再雇用による給与
60歳の定年後、希望すれば65歳まで再雇用の形で同じ会社に勤められます。一般的に、定年前よりも給与は低くなります。 - 再就職による給与
60歳の定年後、あるいは65歳で再雇用が終了した後に、再就職することで給与が得られます。正社員の他、パート、アルバイトなど、体調等に合わせた働き方を選ぶ人が多いでしょう。一からスタートするため、一般的に、給与は定年よりも低くなります。 - 起業による収入
定年後も、起業することで収入を得る人がいます。自営業には定年がありませんから、いつまでも働き続けられます。
老後資金のシミュレーション
夫婦二人暮らしと、単身者とでは、必要な金額が違ってきます。また、定年の年齢によっても、必要資金の総額が変わってきます。具体例をシミュレーションしてみましょう。
夫婦二人暮らし×定年年齢60歳
60歳で定年を迎え、以後は働かないとすると、65歳までは公的年金のない生活となります。繰り上げ受給も可能ですが、受け取れる年金額が減額となります。ここでは、60歳から繰り上げ受給を行うとしてシミュレーションしてみましょう。
- 夫婦が60歳から90歳まで生きるとして、定年後の生活は30年
- 高齢夫婦二人暮らしの平均支出は月額27万円
- 高齢夫婦の平均的な年金受給額は月額19万円
- 60歳から年金を繰り上げ受給すると、受け取れる年金は通常の7割
以上をベースに計算すると、
【必要な老後資金の総額】
27万円×12ヶ月×30年 = 9,720万円
【公的年金で賄える総額】
19万円×0.7×12ヶ月×30年 = 4,788万円
【公的年金以外で捻出しなければならない金額】
9,720万円-4,788万円 = 4,932万円
となります。
夫婦二人暮らし×定年年齢65歳
夫婦二人暮らしで定年の年齢が65歳、定年後すぐに年金生活に入ることを前提としてシミュレーションします。
- 夫婦が60歳から90歳まで生きるとして、定年後の生活は25年
- 高齢夫婦二人暮らしの平均支出は月額27万円
- 高齢夫婦の平均的な年金受給額は月額19万円
以上をベースに計算すると、
【必要な老後資金の総額】
27万円×12ヶ月×25年 = 8,100万円
【公的年金で賄える総額】
19万円×12ヶ月×25年 = 5,700万円
【公的年金以外で捻出しなければならない金額】
8,100万円-5,700万円 = 2,400万円
となります。
夫婦二人暮らし×定年年齢70歳
70歳まで頑張って働き、本来なら65歳からもらえる公的年金を70歳までもらわなかったとしましょう。年金をもらえる年齢を、65歳を超えて指定することを繰り下げ受給といいます。毎月の受給額は、通常よりも増えます。ここでは、70歳から年金をもらう繰り下げ受給を行ったとして計算します。
- 夫婦が70歳から90歳まで生きるとして、定年後の生活は20年
- 高齢夫婦二人暮らしの平均支出は月額27万円
- 高齢夫婦の平均的な年金受給額は月額19万円
- 70歳からの繰り下げ受給にすると、もらえる年金額は1.42倍になる
以上をベースに計算すると、
【必要な老後資金の総額】
27万円×12ヶ月×20年 = 6,480万円
【公的年金で賄える総額】
19万円×1.42×12ヶ月×20年 = 6,475万2,000円
となり、公的年金以外で捻出しなければならない金額は、ほぼなくなります。
一人暮らし×定年年齢60歳
高齢単身無職世帯(60歳以上)の消費支出の平均額はおよそ13万9,000円。社会保険給付の平均額は11万5,000円ほどです(総務省調査)。60歳の時点で年金を繰り上げ受給したとみなして、シミュレーションしてみましょう。
- 単身者が60歳から90歳まで生きるとして、定年後の生活は30年
- 高齢単身無職世帯の平均支出は月額13万9,000円
- 単身者の平均的な年金受給額は月額11万5,000円
- 60歳からの繰り上げ受給にすると、もらえる年金額は7割になる
以上をベースに計算すると、
【必要な老後資金の総額】
13万9000円×12ヶ月×30年 = 5,004万円
【公的年金で賄える総額】
11万5000円×70%×12ヶ月×30年 = 2,898万円
【公的年金以外で捻出しなければならない金額】
4,170万円-2,898万円 = 2,106万円
となります。
一人暮らし×定年年齢65歳
単身者が再雇用制度などを利用して65歳まで働き、後は年金生活に入る場合のシミュレーションをします。
- 単身者が65歳から90歳まで生きるとして、定年後の生活は25年
- 高齢単身無職世帯の平均支出は月額13万9,000円
- 単身者の平均的な年金受給額は月額11万5,000円
以上をベースに計算すると、
【必要な老後資金の総額】
13万9000円×12ヶ月×25年 = 4,170万円
【公的年金で賄える総額】
11万5000円×12ヶ月×25年 = 3,450万円
【公的年金以外で捻出しなければならない金額】
4,170万円-3,450万円 = 720万円
となります。
一人暮らし×定年年齢70歳
単身者が70歳まで勤め上げ、公的年金に関しては70歳からの繰り下げ受給を行ったとしましょう。
- 単身者が70歳から90歳まで生きるとして、定年後の生活は20年
- 高齢単身無職世帯の平均支出は月額13万9,000円
- 単身者の平均的な年金受給額は月額11万5,000円
- 70歳からの繰り下げ受給にすると、もらえる年金額は1.42倍になる
以上をベースに計算すると、
【必要な老後資金の総額】
13万9000円×12ヶ月×20年 = 3,336万円
【公的年金で賄える総額】
11万5000円×1.42×12ヶ月×20年 = 3919万2,000円
となり、公的年金以外で捻出しなければならない金額はなくなります。
参考:「2019年家計調査報告(家計収支編)」(総務省)
参考:「令和元年度 生活保障に関する調査」(生命保険文化センター)
老後資金に備える準備
老後、持ち出しの費用がかなり多くなると感じている人は、以下の3つを準備しましょう。
定期預金
投資をするのも怖いという人におすすめなのが定期預金です。金利は少ないですが、老後のために毎月少しずつ貯めることができるので、自分で将来のための資産を天引するような気持ちで始められます。
財形年金貯蓄
会社側が行う、賃金から天引きで行う財形年金貯蓄であれば、意識しないうちにまとまった資金となります。利子等に対して非課税措置も受けられるので、会社に制度がないか確かめてみましょう。
リバースモーゲージ
自宅を担保に借り入れを行い、死後、自宅を売却することで返済を行います。持ち家を相続する人がいない、子どもへのコスト負担になるといった人は、検討してみましょう。
リバースモーゲージとは? 仕組みとメリットやリスクなど注意点をわかりやすく解説!
健康第一で働き続けられる期間を延ばそう
シミュレーション結果からわかるのは、長く働けば働くほど、持ち出しの負担が軽くなるということです。たとえ、今から節約生活に励んでお金を貯め始めたとしても、粗末な食事で身体を壊してしまっては、元も子もありません。働けなくなってしまえば、資産を削るだけの生活が待っています。
節約を意識するのは大事ですが、健康に気を遣い、食生活と運動を大切にした生活を送りましょう。それが、長く元気に働くための秘訣です。投資や個人年金、融資の勉強をして、無理なくお金を増やすために知識を得るのも大事です