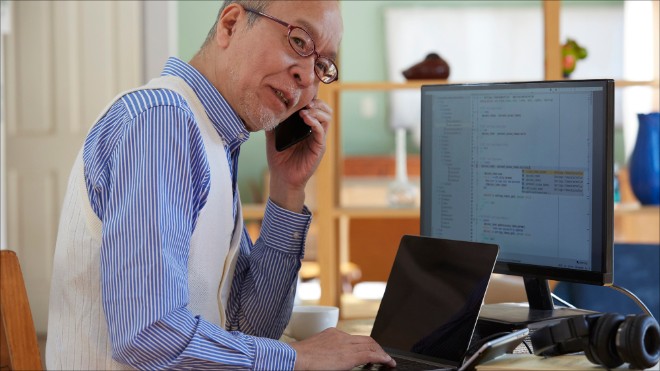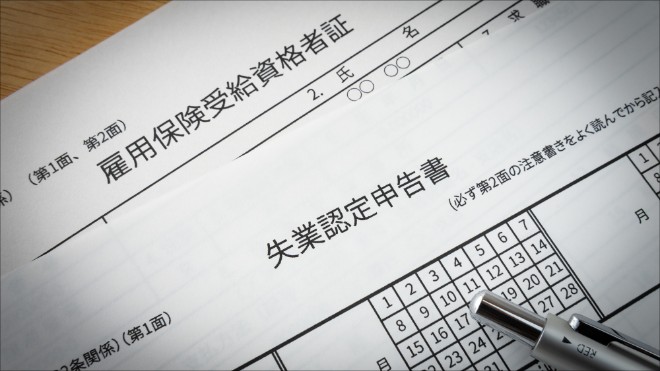生活が苦しく、「生活保護を受けたい」と考えても、「持ち家があると申請できない?」「車を持っているとだめなのだろうか」と、申請を躊躇してしまう人もいることでしょう。持ち家があっても、車を持っていても、生活保護を申請できる場合があります。
また、年金暮らしでも、生活保護を受けることは可能です。生活保護を受けるための条件や、保護してもらうことによるメリット、デメリットについて解説します。
生活保護を受けられる条件
生活保護の対象となるのは、「資産や能力など全てを活用してもなお生活に困窮する」人です。例えば、以下のような人を指します。
- 不動産、自動車、預貯金などのうち、ただちに活用できる資金がない
ただし例外的に居住に必要な持ち家や、車がなければ生活が困難な地域での自動車の保有などについては、認められる場合があります。 - 仕事をしていても、あるいは年金や手当など社会保障給付を活用しても必要な生活費を得られない
- 配偶者や親、子といった扶養義務者からの扶養がなされない
同居していない親族に相談してからでなければ申請できないわけではありませんが、とくに近親者においては、福祉事務所から直接、扶養できないかの確認が行われます。
また、兄弟姉妹、三親等以内の親族へは、援助ができないかどうか照会されることがあります。 つまり、年金生活者であっても、公的年金を含めた社会保障給付では必要な生活費を得ることができず、活用できる資産がなく、また扶養してくれる縁者もいない場合は、生活保護を受けることができます。 以上の条件を満たしたうえで、生活保護が受けられるかどうかの判断については細かな規定があり、自治体の福祉事務所に直接相談して確かめる必要があります。
参考:生活保護を申請したい方へ( 厚生労働省)
生活保護制度(厚生労働省)
生活保護で支給される金額
生活保護で支給される金額は、その地域の級地区分や世帯の構成、月々の収入額によって違います。算出は、以下の順番で行います。
居住地の級地区分を確認する
級地区分とは、必要な生活費が高い地域から順に級数で表した指標です。
級数が高くなるほど、物価や生活水準が高い地域とみなされます。低くなるほど、必要な生活費は低いとみなされます。
世帯の人員や年齢に応じて最低生活費を算出する
最低生活費は、以下の全てを合算した金額となります。
- 生活扶助基準額
食費や光熱費、被服費といった日常生活に必要な費用を算出します。級地と年齢、世帯の人員により、金額基準は細かく定められています。
参考:生活保護制度の概要等について(P.9~) - 加算額
障がい者がいる、母子世帯である、児童を養育しているといった事情がある場合に、級地に応じて加算されます。 - 住宅扶助基準
家賃についても、級地に応じて基準額があり、基準額の範囲内で実費相当額が計上されます。 - 教育扶助基準、高等学校等就学費
小、中、高校生いずれも基準額があり、その他必要に応じて教材費やクラブ活動費、入学金などの実費が計上されます。 - 介護扶助基準
居宅介護等にかかった介護費の平均月額が計上されます。本人負担はなしです。 - 医療扶助基準
診療等にかかった医療費の平均月額が計上されます。本人負担はなしです。
以上、本人負担がない2項目を含めない、計4項目の基準額を合算して月々の最低生活費を出します。他、相殺費用や就労に必要な技能の習得等にかかる費用、出産費用については、定められた範囲内で実費が支給されます。
最低生活費から、得られる収入額を引いた部分が支給される
年金や手当、働いて得られる金額等を計算し、最低生活費に満たない部分が、生活保護費として支給されます。
生活保護と年金を受給する場合の注意点
生活保護と年金を同時に受給したいと考えたら、以下の2点に注意しましょう。
家のローンを支払っている間は受給が難しい
持ち家があっても申請はできますが、家のローンが残っていると、申請が通りにくくなります。毎月の返済額が厳しいのであれば、生活保護の受給を考える前に、ローン返済対応などを金融機関に相談したほうがよいでしょう。
他に利用できる制度がないかあらかじめ調べておく
「お上の世話になるなんて」と気が進まない人にとっては、福祉事務所の窓口を訪問することすらハードルが高いでしょう。しかし他に利用できる制度がないかどうか、あらかじめ調べておくことで、生活保護を受ける必要がなくなるかもしれません。
例えば、自宅を担保に融資を受けられるリバースモーゲージという制度があります。月々、必要な金額を少しずつ借りても良いですし、一括でまとまった金額を借り受けても良いものです。加えて月々の返済は利息のみ、金融機関によっては利息の返済も不要なので、無理なく利用することができます。元金や返済していない利息は、亡くなった後に自宅を売却することで返済できます。
また、リースバックは自宅を売却した後も家賃を支払うことで、住み慣れた家に暮らし続けられる制度です。他人名義の家になるため、固定資産税や修繕費等を支払う必要がなくなります。
生活保護を受けるメリットとデメリット
生活保護を受けるメリットとデメリットを、それぞれ解説します。
生活保護を受けるメリット
- 必要最低限の生活費を確保できる
これが一番大きなメリットになります。わずかな金額であっても、「明日、食べていけるかどうか」と悩む人にとっては大きな安心につながるでしょう。
- 医療費、介護費が無料になる
国民健康保険への加入資格を失うため、保険証はなくなります。そのかわり、福祉事務所で発行される医療健を使って受診することになります。また、介護サービスの料金については、通常は1割から3割負担ですが、被保護者はゼロになります。
- 税金が免除される
住民税や固定資産税が免除されます。NHKの聴取料も徴収されません。
生活保護を受けるデメリット
- 疎遠になっている親族にも扶養照会がなされる
福祉事務所により、三親等以内の縁者へ「扶養や援助が可能ではないか」といった連絡が入る可能性があります。自分が困窮している状況が、親戚に知れ渡ってしまうことになります。
- 生活費の使い方に関して福祉事務所に報告しなければならない
生活保護を受けている間は、福祉事務所の訪問を受けたら、収入や支出の状況について報告しなければなりません。支出については、投資目的のような大きい買い物をしない限り、見とがめられることはありませんが、「監視されている」と感じ、負担に思う人もいるでしょう。
- 引越ししなければならないケースがある
今住んでいる物件の家賃が、扶助の範囲を超えてしまうくらい高いものだと、安い物件への引越しを求められるかもしれません。ただ、年金生活者は新たな賃貸契約を結ぶのが難しいもの。なかなか契約に至らない場合は、福祉事務所の担当者に相談しましょう。
年金者ほど生活保護が必要な場合が多い
年金生活が苦しく、「まさか、この年になって生活保護を検討するとは」と思っている人もいるかもしれません。しかし、厚生労働省「被保護者調査(2019年度確定値)」 によると、生活保護を受けている人の半分以上が高齢者世帯です。
そのくらい、年金生活は苦しいということを表しています。 今後の生活が不安になった段階で福祉事務所に相談すれば、貧困に陥らないための対策を一緒に立ててもらうことも可能です。
また、いざ生活保護を申請する段階になったときにも、自分の状況をよく知っている担当者がいれば親身になってもらえるでしょう。窮地でなくても、地域の福祉担当者にアドバイスをもらうことなどを目的に、まずは福祉事務所に話をしてみてはいかがでしょうか。