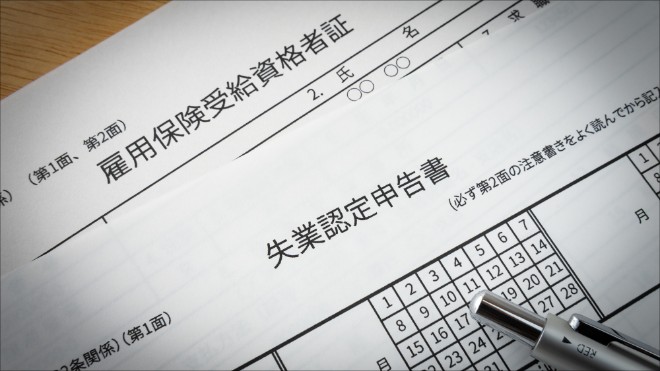成年後見人制度という言葉を聞いたことがありますか? じつは認知症の家族を介護する人にとって、とても重要な制度です。そんな制度の仕組みと、認知症などの判断力が十分ではない方をサポートする成年後見人の決め方や、基本報酬や付加報酬などの報酬の仕組み・金額についてまとめてみました。毎月の支払いとなる成年後見人への支払い金額は、家族にとっても無視できない問題です。制度活用のためにも把握しておきましょう。
成年後見人の決め方
成年後見制度は、2000年4月1日に介護保険制度と同時にスタートしました。介護保険が始まると、高齢者自身が介護施設への入所契約や財産管理をする必要が出てきます。しかし認知症の人には、こうした判断が難しいことから高齢者をサポートする目的で発足したのです。
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分ではない人のサポートする制度なので、財産管理や介護サービスや施設への入所に関連する契約などを支援します。そのため介護などの業務は担当しません。
一方、悪徳手法から認知症患者を守るために、成年後見制度が活用されてきたといった歴史はあります。
成年後見制度は、大きく2種類に分かれます。「法定後見制度」「任意後見制度」です。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症患者などをサポートする成年後見人を裁判所が選出します。選ばれるのは親族だけではなく、弁護士などの法律の専門家や社会福祉士などの福祉の専門家、あるいは福祉関係の公益法人などのケースもあるようです。また複数の成年後見人が選ばれることもあります。
任意後見制度
一方、任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、自分が選んだ成年後見人と契約を結んでおき、実際に判断能力が低下したときに保護支援を始めるといった制度です。
ただし成年後見人は大きな権限を持つだけに、家庭裁判所が認めたときは後見監督人を選ぶことができるようになっています。近年は管理する財産が多い場合などは、後見監督人がつくケースが増えているようです。
任意後見人は成人であれば、破産者や本人と訴訟した人といった特殊なケースをのぞき、誰でも指名することができます。一般的には、親族や弁護士などの法律の専門家が多いようです。
ただ、法定後見制度で親族が家庭裁判所から選任されるケースが減っています。2000年は親族の割合が91%だったのに、2019年には22%まで落ち込んでいるのです。これは親族の成年後見人による財産の着服といった事件が相次いだからです。結果、弁護士や司法書士などの専門家を、裁判所が選任するケースが増えているのです。
こうした傾向を考えると、確実に親族に成年後見人をお願いしたいと考えるなら、任意後見制度で契約を結んでおく方がいいでしょう。
成年後見人の不動産売却に関して
さて、成年後見人は財産の管理を担っていますので、住居ではない不動産を売却することができます。一方住居は、たとえ当人が介護施設に入っていたとしても、家庭裁判所の許可がなければ成年後見人による売却はできません。
これと同じような構図で、自宅を担保に銀行から融資を受けて生活資金などにするリバースモーゲージを活用する場合も、裁判所の許可が必要になります。
リバースモーゲージとは? 仕組みとメリットやリスクなど注意点をわかりやすく解説!
法定後見制度の報酬額の相場
成年後見人の報酬は、サポートされている人の財産から支払われます。報酬の金額は、家庭裁判所が判断することになっています。
近年、人数が増えている弁護士や司法書士などの専門家の法定後見人は、裁判所が以下のような基準を公表しています。
| 本人の金融資産 | 報酬(月) |
| 1000万円以下 | 2万円 |
| 1000~5000万円 | 3~4万円 |
| 5000万円より上 | 5~6万円 |
ただし2020年に最高裁裁判所は、法定後見人の報酬額について、業務量や業務の難易度が報酬に反映するように改定を促しています。特に金融資産ごとの料金設定は問題があるとも報道されており、報酬の枠組みは変わる可能性が高そうです。
ちなみに親族が法定後見人となった場合の相場は月「2~6万円」です。
ただし親の財産を減らしたくないと考える人も多く、無償で引き受けているケースがかなり多いようです。
任意後見制度の報酬額の相場
サポートを受ける人との契約で成年後見人となる任意後見制度の報酬は、どれぐらいでしょうか?
当事者間の契約で報酬金額は決まるので、いくらでもいいのですが、親族の場合が月額「2万円~3万円」、司法書士や弁護士などの専門家は月額「3万~5万円」程度です。専門家を頼む割には、それほど高額ではないと感じる人も多いのではないでしょうか?
ただ認知症介護の場合、家族だけでの介護は難しいケースも多く、介護保険サービスの自己負担額が、それなりに高くなるケースがあります。そうした状況での月額数万円の支払いは、負担も大きいと感じる人も少なくないようです。
付加報酬が必要な場合と相場
成年後見人の報酬は、先ほどお伝えしたような月額の基本報酬だけではありません。成年後見人が特別な働きをした場合には、それに合わせて「付加報酬」と呼ばれるものが加算されます。
今後、これも報酬額の見直しが行われる可能性が高いのですが、一応、裁判所が出している法定後見制度の目安を書いておきます。
特別困難な事情がある場合
基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加
【具体例】
- 収益不動産が多数あり、その管理が複雑
- 親族間に意見の対立があり、その調整が必要
- 本人の生活や療養看護に関する事務が困難
- 以前に成年後見人等の不正があり、後任としてその対応が必要
サポートされる人の財産を増やした場合
内容に応じて、増えた財産の30%の範囲内で増減
【具体例】
- 訴訟
本人が不法行為による被害を受けたとして、加害者に対して1000万円の損害賠償請求訴訟を提起。勝訴して、財産が1000万円増えた場合
⇒約80~150万円を付加 - 遺産分割調停
配偶者が死亡したことによる遺産分割の調停が成立し、総額約4000万円の遺産のうち約2000万円相当の遺産を取得
⇒約55~100万円を付加 - 居住用不動産の任意売却
本人の療養看護費用を捻出する目的で、その居住用不動産を、家庭裁判所の許可を得て3000万円で売却
⇒ 約40~70万円
今後、報酬岳がどのようになるのか予断を許さない状況ですが、各人の出せる金額が大きく変わることもないため、報酬を大幅にアップするのは難しいといった報道もあります。成年後見制度は認知症などの人々を社会的にバックアップするものなので、制度変更も注目しておく必要がありそうです。